
百人一首かるたの歌人エピソード第83番・皇太后宮大夫俊成~つらい時代だからこそ見えてくる美しい世界”幽玄”
世の中よ 道こそなけれ 思ひ入る 山の奥にも 鹿ぞなくなる
”末法”の到来と言われた平安末期、貴族たちは現世に希望を見いだせなくなった一方で、内面的な美しさ”幽玄”を探求していきました。百人一首かるたの歌人エピソード、今回ご紹介いたします第83番・皇太后宮大夫俊成(こうたいごうぐうのだいぶとしなり)は、そんな時代を代表する歌人です。
平安末期最大の歌人、藤原俊成(1114~1204)
皇太后宮大夫俊成(こうたいごうぐうのだいぶとしなり)の本名は、藤原俊成といいます。小倉百人一首の選者、藤原定家の父上で、かの権力者、藤原道長の玄孫にあたります。
俊成は第86番・西行法師と並ぶ、平安末期最大の歌人といわれています。俊成は、”幽玄”という世界観を定着させた人物として知られ、その考え方は、後世の和歌や茶道、能楽といった日本文化に大きな影響を与えることになりました。

竹島園地(愛知県蒲郡市)の藤原俊成像
俊成が生きたのは、平安時代末期から鎌倉時代初期。武士が台頭して世の中は混乱、貴族や僧侶たちは”末法”の時代が始まったと考えました。一方で、貴族を中心とした文化は成熟し、より深い精神性や美意識が求められるようになっていきました。時代の混乱と精神的な探求が、日本文化において”幽玄”という概念の広がりに大きな影響を与えたようです。
”幽玄”とは、もともと仏教や中国の老荘思想から来た哲学的な思想です。俊成は”幽玄”を言葉に表れない深くほのかな余情ととらえ、日本ならではの美意識として発展させたと言われています。
この世には、悲しみやつらさを逃れる方法などないものだ。思いつめたあまりに分け入った山の奥でさえ、悲しげに鳴く鹿の声が聞こえてくるではないか。
小倉百人一首に選ばれた歌は、藤原俊成が「千載集」に自ら選んだ自信作で、27歳の時の作品です。平安時代、世の中のつらさから逃げる方法は、世俗を離れて仏門に入ることでした。俊成と親交のあった西行法師を始め、何人もの俊成の友人が次々と出家していきました。
俊成は山の奥に入ることと仏門に入ることをかけ合わせ、そこで聞こえてきた悲し気な鹿の鳴き声を表現することで、出家していく友人たちとの別れの悲しみを、悲しいという言葉を使わずに表現しています。

藤原俊成が晩年住んでいた京都市伏見区・深草周辺
俊成は、息子の藤原定家をはじめ、寂蓮、後鳥羽院、式子内親王など、優秀な歌人を育て、指導者としても大きな功績を残しました。亡くなる直前まで精力的に歌を詠み続けた藤原俊成は、91歳という長寿を全うしました。
☆こちらの記事は、”幽玄”の世界観を確立したもうひとりの人物、第85番・俊恵法師をご紹介しております。
夜もすがら もの思ふ頃は 明けやらで ねやのひまさへ つれなかりけり
恋しさが募って夜も眠れなくなる・・・1000年の時を隔てても、変わらない想いですね。だからこそ、今も残る優れた和歌の多くが、恋をテーマにしているのでしょうか。
情報源: 百人一首かるたの歌人エピソード第85番・俊恵法師~多くを語らず余情を重んじる、”幽玄”の世界へようこそ ⋆ MUSBIC/ムスビック
MUSBIC公式 Facebook ページ



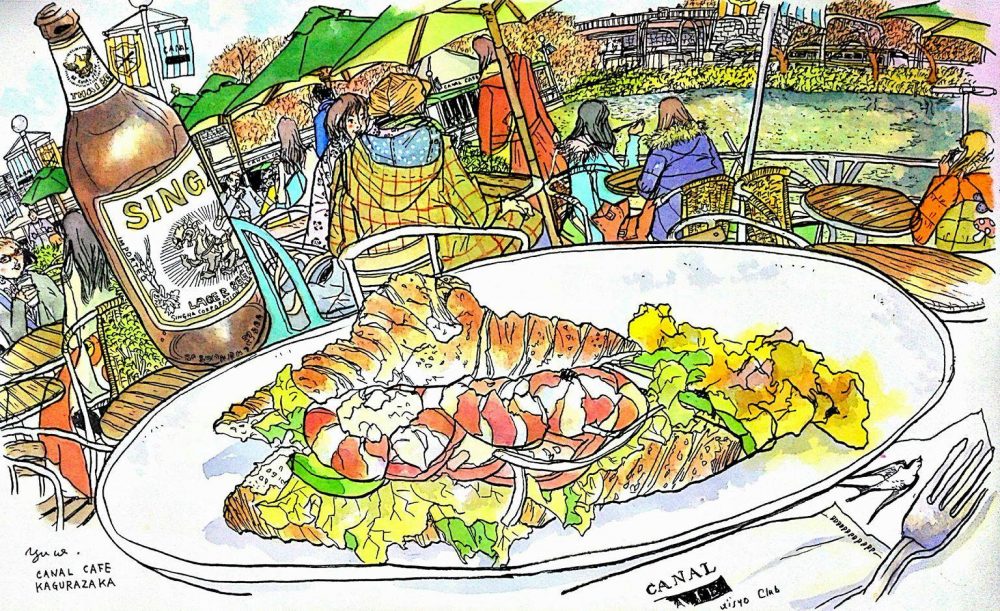



この記事へのコメントはありません。