
百人一首かるたの歌人エピソード第89番・式子内親王の静かなる情熱
玉の緒よ たえねば絶えね ながらへば 忍ぶることの 弱りもぞする
心に秘めた情熱は、誰にも止めることはできません。たとえ時代の波に翻弄され、生きたいように人生を謳歌できなくても!
”畳の上の格闘技”、競技かるたに使われる百人一首かるたに登場する女性皇族、第89番・式子内親王が歌に封じ込めた情熱とは・・・?
乱世に翻弄された皇女、式子内親王
小倉百人一首に選ばれている女性の歌は、21首。そのうち女性皇族は、第2番・持統天皇と式子内親王だけです。式子内親王は、後白河院の皇女で、以仁王の同母妹、安徳天皇の伯母にあたります。
お名前「式子」の読み方はわかっていません。「しきし」「しょくし」「のりこ」「しきこ」等、様々な説があります。

式子内親王(出展:Wikimedia Commons)
式子内親王は、11歳から10年間、上賀茂神社と下鴨神社で神様に仕える「斎院(さいいん)」を務めました。斎院は、任期中は独身でなければならず、退任後も皇族や最上級の貴族としか結婚は許されません。
式子内親王が斎院を辞めた後は、兄の以仁王は平家打倒の挙兵をしたものの討ち死に、甥の安徳天皇は入水、という源平争乱の真っただ中。式子内親王ご自身も伯母と姪を呪ったというあらぬ疑いをかけられ、父の許しを得ずに出家してしまいました。この世の無常を数多く経験なさった女性でもあります。
私の命よ、絶えるなら絶えてしまいなさい。生きながらえていると絶えることができなくなり、恋心が外に表れてしまうかもしれないから。
式子内親王の歌は、百人一首随一の”忍ぶ恋”の歌と言われています。でも相手が誰なのか、わかっていません。平安時代後期の特徴である「題詠」(お題を与えられて詠む歌)であり、フィクションだというのが通説ですが、これほどまでに激しく秘めた思い、まったくの無経験だったら詠めないのでは?なんて思ってしまいますね。
小倉百人一首の選者、藤原定家や、浄土宗の開祖、法然がそのお相手ではないかという研究もありますが、いずれも推測の域を出ていません。
式子内親王は、歌会に参加した記録はほとんどないのに、歌人としての評価が非常に高い方です。第99番・後鳥羽院は、「近き世のことさらなる歌人」として、第91番・後京極摂政前太政大臣(藤原良経)、第95番・前大僧正慈円とともに式子内親王をあげて賞賛しています。近年では、愛子さまが卒業論文のテーマになさったというニュースもありましたね!
☆こちらの記事は、式子内親王の”忍ぶ恋”のお相手?かもしれない、藤原定家をご紹介しております。
来ぬ人を まつほの浦の 夕なぎに 焼くや藻塩の 身もこがれつつ
いよいよ小倉百人一首の選者が登場!畳の上の格闘技、競技かるたで使われる小倉百人一首、第97番の権中納言定家こと藤原定家(1162-1241)をご紹介いたします。
情報源: 小倉百人一首の選者登場!~百人一首かるたの歌人エピソード第97番・権中納言定家(藤原定家)は、”神”と讃えられたり嫌われたり!? ⋆ MUSBIC/ムスビック
MUSBIC公式 Facebook ページ



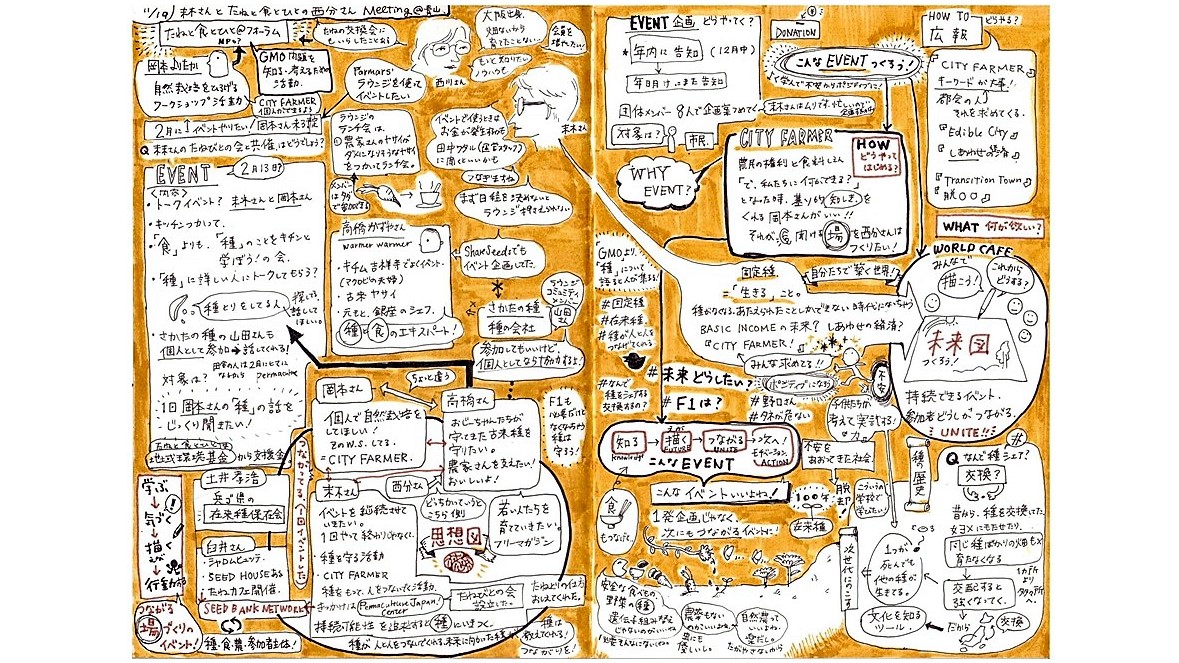



この記事へのコメントはありません。